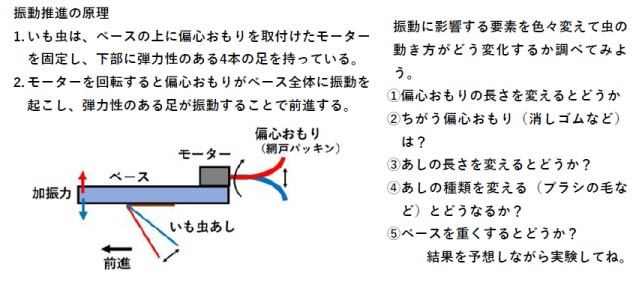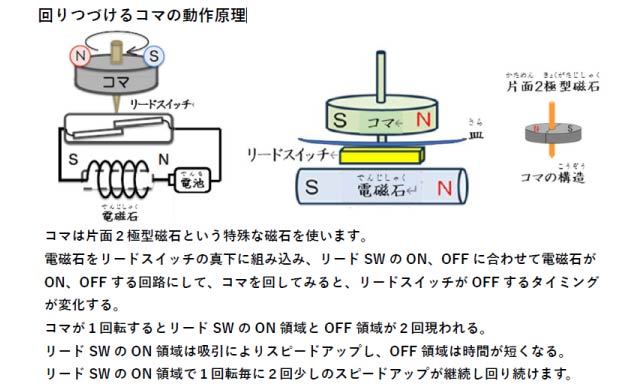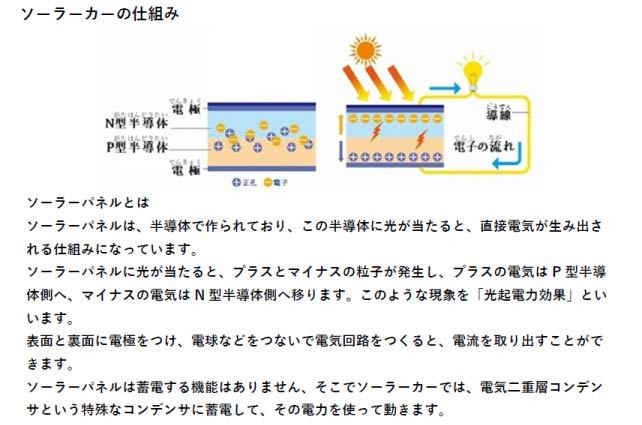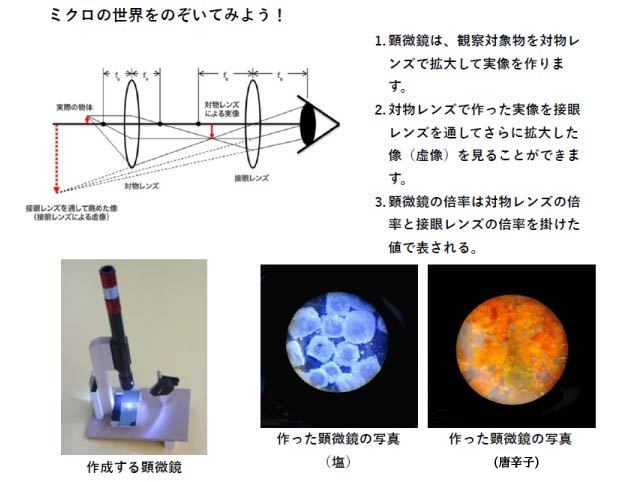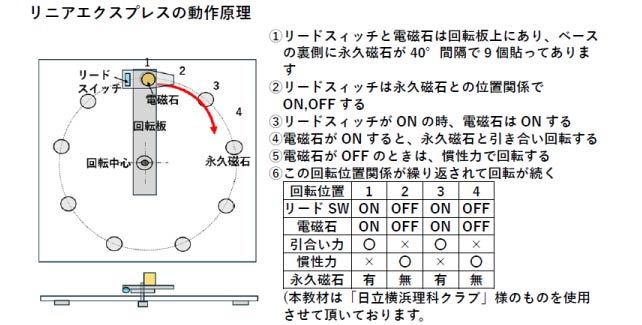募集作品紹介
2026年1~3月教室開催予定の作品を紹介しますので、応募する際の参考にしてください。
1~3月分モノづくり教室の申し込み期間は12月6日~12月14日です。
2026年1~3月教室開催予定の作品を紹介しますので、応募する際の参考にしてください。
1~3月分モノづくり教室の申し込み期間は12月6日~12月14日です。
2026年1~3月教室開催予定の作品を紹介しますので、応募する際の参考にしてください。
1~3月分モノづくり教室の申し込み期間は12月6日~12月14日です。
2026年1~3月教室開催予定の作品を紹介しますので、応募する際の参考にしてください。
1~3月分モノづくり教室の申し込み期間は12月6日~12月14日です。